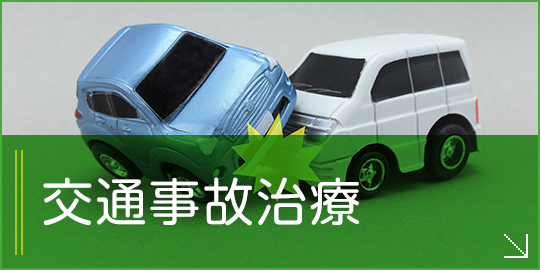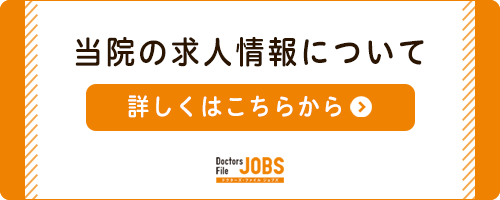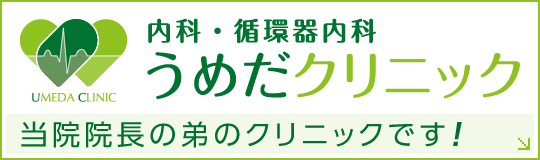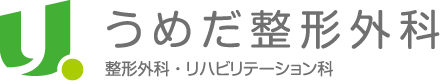前回のコラムでは、カルシウムの吸収を助けるビタミンDの重要性についてお話しました。
骨の健康を考える上で、カルシウム、ビタミンDと並んで見逃せないもう一つの重要な栄養素があります。それが「ビタミンK」です。
ビタミンKは、摂取したカルシウムを骨に定着させる重要な役割を担っており、骨粗しょう症予防において欠かすことのできない栄養素です。しかし、その重要性についてはあまり知られていないのが現状です。今回は、この「隠れた立役者」ビタミンKについて詳しくご紹介します。
ビタミンKってどんな栄養素?
ビタミンKは脂溶性ビタミンの一種で、主に2つのタイプがあります。
なぜビタミンKが骨粗しょう症予防に重要なの?
ビタミンKは、摂取したカルシウムを骨にしっかりと定着させる「接着剤」のような働きをします。ビタミンDが「運搬役」なら、ビタミンKは「定着役」といえるでしょう。
具体的には、ビタミンKが骨に存在するオステオカルシンというタンパク質を活性化することで、カルシウムが骨に沈着し、骨からの流出を防ぎます。研究では、ビタミンK摂取量が少ない人ほど、骨粗しょう症による骨折リスクが高くなることが報告されています。
手軽にビタミンKを摂取する方法
忙しい日常生活の中でも、以下の工夫でビタミンKを効率的に摂取できます。
吸収率を高める調理のコツ
ビタミンKは脂溶性で熱に強い性質を持つため、以下の調理法がおすすめです。
ビタミンK摂取時の重要な注意点
血液をサラサラにする薬(ワーファリンなど)を服用している場合、ビタミンKの血液凝固作用が薬の効果を弱めてしまう可能性があります。このような薬を処方されている方は、納豆やビタミンKを多く含む食品の摂取について必ず医師に相談してください。
効果的な組み合わせ摂取
骨粗しょう症の予防には、ビタミンK単体ではなく、カルシウム + ビタミンD + ビタミンKの三位一体で摂取することで、最大の効果が期待できます。
まとめ
ビタミンKは、カルシウムやビタミンDと並んで骨粗しょう症予防に欠かせない重要な栄養素です。特に、摂取したカルシウムを骨にしっかりと定着させる「接着剤」としての役割は、他の栄養素では代用できない独自の働きです。
日本の伝統的な食材である納豆は、世界でも類を見ないほどビタミンKが豊富に含まれており、骨粗しょう症予防において非常に有効な食品です。また、ほうれん草、ブロッコリー、小松菜などの緑黄色野菜も、日々の食事に取り入れやすく、継続的な摂取が可能です。
ただし、血液をサラサラにする薬を服用中の方は、摂取前に必ず医師に相談することが大切です。
骨粗しょう症は「静かな病気」と呼ばれ、症状が現れる前に進行してしまうことが多い疾患です。当院では骨密度測定による早期発見と、患者様一人ひとりのライフスタイルに合わせた総合的な予防プランをご提案しております。ご自身の骨の健康について不安がある方は、お気軽に【うめだ整形外科】へご相談ください。
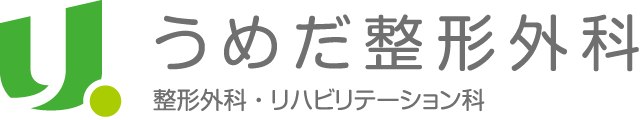
 納豆1パック(40g)で約240μgのビタミンKが摂取でき、1日の必要量を十分に満たせます。ご飯にかけるだけで手軽に摂取できます。
納豆1パック(40g)で約240μgのビタミンKが摂取でき、1日の必要量を十分に満たせます。ご飯にかけるだけで手軽に摂取できます。
 小松菜(30g)をバナナや豆乳と一緒にスムージーにすることで、美味しくビタミンKを摂取可能です。
小松菜(30g)をバナナや豆乳と一緒にスムージーにすることで、美味しくビタミンKを摂取可能です。
 卵料理にほうれん草(20g)を加えることで、タンパク質と一緒にビタミンKを摂取できます。
卵料理にほうれん草(20g)を加えることで、タンパク質と一緒にビタミンKを摂取できます。
 ブロッコリー1個(125g)で約200μgのビタミンKが摂取できます。オリーブオイルと一緒に摂ると吸収率が向上します。
ブロッコリー1個(125g)で約200μgのビタミンKが摂取できます。オリーブオイルと一緒に摂ると吸収率が向上します。
 わかめには豊富なビタミンKが含まれており、毎日の味噌汁に加えることで継続的に摂取できます。
わかめには豊富なビタミンKが含まれており、毎日の味噌汁に加えることで継続的に摂取できます。
 冷凍のほうれん草や小松菜を炒め物や汁物に加えることで、手軽にビタミンKを補給できます。
冷凍のほうれん草や小松菜を炒め物や汁物に加えることで、手軽にビタミンKを補給できます。